現行制度下におけるプログラムの公募は、平成27(2015)年度をもって終了しました
関係各位
平成25年12月20日
日本救急医学会
指導医・専門医制度委員会 谷川 攻一
専門医認定委員会 奥地 一夫
代表理事 行岡 哲男
本年4月以降、日本専門医制評価・認定機構から専門医制度整備指針(第4版)、専門医制度研修プログラム整備指針が相次いで発表されました。その中に「これからの専門医の育成は研修プログラムを基盤に行うこと」が理念として掲げられております。日本救急医学会の新しい専門医制度は2017年実施を目途に段階的に構築されて行くことが予定されています。
そこで、日本救急医学会では新しい専門医制度へ向かう準備段階として、あくまでも現行制度の枠組みの下で、事前登録制のための救急科専門医育成プログラムの公募を試行することとなりました。
また、今回のプログラム公募は上記の通り新制度のための試行ではありますが、後期研修医が事前登録し認定されたプログラムに従って計画的に研修した場合には、救急科専門医新規申請において、他科ローテーション(他科研修)期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めます。なお、今回開始するプログラム登録は、救急科専門医指定施設の要件に加わるものではありません。あくまでも試行段階であり、プログラム登録を希望する施設が任意に利用できるものです。
また、プログラム登録申請が可能な施設は、救急科専門医指定施設に限られます。
【参考資料】
今後のスケジュール
- 2013年12月20日 救急科専門医指定施設からのプログラム登録を受付開始(締切翌年1月末日)
- 2014年2月下旬 専門医認定委員会から登録申請審査結果を通知
- 2014年3月中旬 研修医からの認定されたプログラムへ事前登録受付開始
※その後は、毎年4月1日〜6月30日 救急科専門医指定施設からのプログラム登録を受付ける予定です。研修医からのプログラムへの事前登録については平成26(2014年)3月以降随時受付けます。
事前登録については随時受付の予定でしたが毎年3月1日〜5月31日のみ受付に変更になりましたのでご注意ください。
プログラム作成要領とプログラム例
プログラムを作成するにあたっての要件を示します.
- 基本的考え方
研修プログラムは救急科専門医となるために必要な教育課程を記載したカリキュラムに準拠して、知識、技能の修得が計画性をもって達成できるように専門医研修施設が作成する必要があります.現時点では救急医学会のカリキュラムと表記し文書化したものはありませんが、現行の日本救急医学会・専門医認定制度の救急科専門医診療実績表にあるA.(必要な手技・処置)、B.(必要な知識)C.(必要な症例)が救急科専門医としての要件を示しカリキュラムに相当すると考えられます。これらのA、B、Cについて計画性を持って経験できるように、各施設の特徴を勘案してプログラムを作成して下さい.
- 記載事項
- 研修プログラムの名称
- プログラムの概要
3年同一施設か、他科研修を含むか、その他の特徴を簡単に述べる.
- 教育到達目標
当該施設がどのような救急医を養成の最終目標とするかを記載する.
- 研修施設
- 基幹研修施設(当該施設)、研修プログラム責任者名(救急科専門医)
- 関連研修施設(救急専従する他施設)研修プログラム責任者名
- 他科研修(ローテーション)施設(救急専従しない施設、たとえば外科専従、内視鏡専従等)
指導責任者名もしくは認証資格者名
- 研修プログラム
救急勤務歴3年(36ヶ月)をどのような計画で研修するかを、年度ごとの研修到達目標、指導体制、診療内容、担当領域、特徴などを中心に適宜記載する.原則2年目の初期研修医が対象ですので、彼らに当該施設における研修のアピールしうる事項を中心にまとめて下さい.一施設のみで研修が完結しないときには、他施設での研修を含むプログラムを作成することが可能です.事前登録した場合、救急専従をしない他科研修の診療期間の2分の1を救急勤務歴として算定することができます.
例1.モデル研修プログラム(3年専従型)
- 研修プログラムの名称
○○○○病院 救命救急センター 救急科専門医育成研修プログラム
- プログラムの概要
原則として卒後3年目以降の研修医を対象として、救命センターに3年間専従し救急科専門医の養成を行うための後期研修プログラムである。
- 教育到達目標
救急部門で遭遇する疾病、外傷等の生命の危機にある病態に対する初期対応および診断能力を修得し、重症患者の集中治療を行うことができる救急科専門医となる。
- 研修施設
○○○○病院 救命救急センター
研修プログラム責任者名: ○○○○○
- 研修プログラム
1年目
例2.モデル研修プログラム(複合型:他科研修2年を含む)
- 研修プログラムの名称
○○○○病院 救命救急センター 救急科専門医育成研修プログラム
- プログラム概要
本プログラムは卒後3年目以降の研修医を対象として、外科専門施設と連携し、外科治療を中心に救急医療に携わる救急科専門医の育成を4年間で行うための複合型後期研修プログラムである。
- 教育到達目標
救急医として全て救急患者の初療および入院治療を行うことができ、さらにサブスペシャルティとして急性腹症、腹部外傷の緊急手術が行える救急科専門医となる。
- 研修施設
- 基幹研修施設: ○○○○病院 救命救急センター
研修プログラム責任者名: ○○○○
- 他科研修施設: △△△△病院 腹部・一般外科
指導者: 外科部長 △△△△
- 研修プログラム
1年目(基幹研修施設)
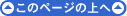
救急科専門医育成プログラムを登録した場合の専門医新規申請までの流れ
| Step 1:救急科専門医育成プログラム登録申請書の提出 |
| プログラム責任者 |
|
専門医認定委員会及びER検討委員会 |
①救急科専門医育成プログラム登録申請書とプログラムを提出する。
注)プログラム運用施設の要件
・救急科専門医指定施設であること
(今回の応募の場合、2014年1月時点で救急
科専門医指定施設であること)
・プログラム責任者が救急科専門医であること |
救急科専門医育成プログラム登録申請書とプログラム

登録申請審査結果報告書 |
②3年専従型及び複合型については、専門医認定委員会で審査する。ER型についてはER検討委員会で審査し結果を専門医認定委員会に報告する。
③専門医認定委員会より、登録申請審査結果報告書 を用いて、審査結果と登録プログラム番号を通知する。 |
| Step 2:研修開始と事前登録の申請(3月〜5月) |
| 後期研修医(専攻医) |
|
専門医認定委員会 |
| ④研修開始後1ヶ月以内に研修開始届(事前登録)を専門医認定委員会に提出する。 |
事前登録申請書

受理書 |
⑤事前登録受理書を発行する。 |
| Step 3:研修修了報告と救急科専門医審査の新規申請(勤務歴審査)(1月〜2月) |
| 専攻医 |
|
専門医認定委員会 |
⑥救急科専門医審査の新規申請時に、研修修了報告書を提出する。
注)別紙5には施設の指導者(救急科専門医もしくは認証資格者)の捺印が必要。 |
修了報告書

合否通知 |
⑦他科ローテーション修了報告書から他科ローテーション期間の1/2(端数切り捨て、最大12カ月)を救急兼任歴に加算する。
⑧救急勤務歴3年以上(うち、救急専従歴1年以上必須)を満たしていれば,勤務歴(第1次)審査は合格とする。救急勤務歴の定義については日本救急医学会専門医認定制度規定参照のこと。 |
Q&A
≪救急科専門医育成プログラム登録についてのQ&A≫
Q:救急科専門医指定施設は必ず研修プログラムを登録しなければいけないのですか
A:必須ではありません
Q
:自施設以外で研修をする場合、プログラムを登録する段階でその施設と契約をしておく必要はあるのですか?
A
:プログラム登録時の研修先は予定で結構ですので、契約する必要はありません。ただし、研修先・期間等に変更があった場合でも、救急科専門医新規申請時に、救急勤務歴3年(36ヶ月)を満たしているようご注意ください。
Q:後期研修医はさまざまな他科研修を希望します。プログラムの登録申請書はそれぞれの科ごと、期間ごとに分けて提出する必要がありますか。
A:科(あるいはローテ期間)ごとに細かく分けて提出する必要はありません。
研修期間・研修場所については、代表的な例を記載いただき、添付いただくプログラム内容に詳細を記載ください。もし、プログラムの特色がまったく異なる場合には、それぞれ別のプログラムとしてご提出ください。
Q:登録したプログラムでは他科研修は内科12ヶ月と記載していたが、実際の研修は内科6ヶ月、麻酔科6ヶ月となったというように他科研修先に変更があった場合や、内科12ヶ月の予定が10ヶ月になったように他科研修期間に変更があった場合など、登録したプログラムと実際の研修が異なった場合はどうなりますか。
A:原則として、登録したプログラムと実際のプログラムが違っていても、研修医が事前登録をしていれば、他科研修期間の半分(上限12ヶ月)を救急勤務歴(兼任歴)として認めます。救急科専門医申請時に申請者より実際の他科ローテーションを提出していただきますので、それを審査して救急勤務歴の計算をし、救急勤務歴(救急専従歴+救急兼任歴)が3年あれば救急勤務歴審査は合格です。ただし、救急科専門医の研修としては余りに偏っているもの(例:他科研修期間2年がすべて眼科のみ等)の場合には、不可とする場合があるため、「登録したプログラムと実際にプログラムのどこまで変更をみとめるかは、最終的には専門医認定委員会での審査にて決定」とさせていただいております。
Q:救急科専門医育成プログラム登録申請書に「救急科専門医審査(勤務歴・診療実績)時において、ローテーション先施設に常勤する救急科専門医(不在の場合は認証資格者)の証明が必要となるので注意のこと」あるのはどういうことでしょうか。
A:現行の救急科専門医制度において、「指導者とは:申請時にその施設に勤務する救急科専門医(不在の場合は認証資格者)のことをいう。」と定義され、必ずしも診療に関する実際の指導者を指すわけではありません。救急科専門医新規申請の第1次(救急勤務歴)審査および第2次(診療実績)審査において、申請者が申請する施設について指導者による証明が必要となり、指導者が不在の施設での証明は認めらません。救急科専門医申請時に救急科専門医が不在の場合は、どなたかに認証資格者になっていただく必要がありますので注意が必要とのことです。
≪後期研修医の事前登録についてのQ&A≫
Q:事前登録をしていないと、救急科専門医申請ができないのですか
A:いいえ。救急勤務歴3年以上を満たせる場合には、従来通り、事前登録を利用しなくても救急科専門医申請ができます。事前登録する方法と事前登録しない方法の2種類になるということです。
Q:3年間救急部門に専従している場合も研修プログラム登録や事前登録をしなければいけないのですか
A:いいえ。3年専従型のプログラム登録も受付けてはおりますが、必須ではありません。従来通り「救急勤務歴3年以上」があればプログラム登録・事前登録をしなくても、救急科専門医に申請ができます。
Q:事前登録した場合、他科ローテーション期間中の症例を第2次(診療実績)審査で使うことができるのですか
A:できます。
Q:登録していたプログラムとは実際の研修が違ってしまった場合はどうすればよいのですか
A:救急科専門医申請時に「救急科専門医育成プログラム修了報告書(他科ローテーション)」をご提出いただきますので、そこに実際修了した他科ローテーションをご記載ください。専門医認定委員会にて、審査します。
Q:事前登録をしていないと、他科ローテンション期間は救急勤務歴(兼任歴)にならないのですか?
A:いいえ。救急に関与していた場合は、救急兼任歴として下記の換算方法により救急勤務歴に加算することができます(これは従来通りで変更ありません)。
(月数)×X/6
・「X」:週の関与回数 ※週2回までとし、3回以上の関与は認めない。
・勤務形態の「1日」「半日」「夜間」の区別なし
Q:事前登録した場合には、他科ローテーション期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めるというのはどういうことですか。
A:救急兼任歴については事前登録をしていなくても(月数)×X/6(X:週の関与回数)という計算方法により救急勤務歴に加算できますが、Xは2回までしか認めていないことから、例えば、現在は2年専従+2年兼任(24ヶ月×週2回/6=8ヶ月の勤務歴)では救急勤務歴2年8ヶ月のため申請資格が得られないけれども、今回の制度を利用することにより、2年救急専従+2年他科ローテーション(24ヶ月の5割=1年の勤務歴)で救急勤務歴3年となり申請資格を得られるようになります。ただし、いずれにせよ救急兼任歴の配点は0点です。
Q:今回救急科専門医育成プログラム登録を自分の施設が申請する予定です。これを機会に、事前登録を申請する予定ですが、以前の他科ローテーション期間についても5割(合計最大1年)は救急勤務歴(兼任歴)に加算できるのですか。
A:いいえ。事前登録以前の他科ローテーションについては従来通りの扱いになりますので、救急に関与していた場合のみ、救急兼任歴として下記の換算方法により救急勤務歴に加算します。
(月数)×X/6
・「X」:週の関与回数 ※週2回までとし、3回以上の関与は認めない。
・勤務形態の「1日」「半日」「夜間」の区別なし
Q:後期研修医が事前登録し認定されたプログラムに従って計画的に研修した場合には、救急科専門医新規申請において、他科ローテーション(他科研修)期間の5割(合計最大1年間)を救急勤務歴(兼任歴)として認めるとありますが、他科ローテーションが2年以上の場合はどのような扱いになるのですか?
A:合計最大1年間ですので、2年以上の場合は1年間の救急勤務歴(兼任歴)として扱います。
他科ローテーション(他科研修)の換算例:
例1)他科ローテーション期間が計24カ月の場合、12カ月の救急勤務歴(兼任歴)として認める。
例2)他科ローテーション期間が計23カ月の場合、11カ月の救急勤務歴(兼任歴)として認める(1ヶ月未満は切り捨てる)。
例3)他科ローテーション期間が計26カ月の場合、13カ月ではなく、12カ月の救急勤務歴(兼任歴)として認める(最大12カ月まで)。
お問い合わせ
救急科専門医育成プログラム公募に関するお問い合わせはメールで受け付けております。
E-mail: jaam99-gakkai@umin.ac.jp 現在このメールは使えません
・メールの件名を「プログラム質問」としてください。
・氏名、所属、電話番号を明記してください。
|

