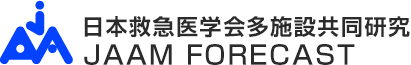概要
1.研究の概要
敗血症
日本救急医学会は、2010〜2011年にかけて重症敗血症の多施設共同前向き調査研究を行った。その結果、日本の重症敗血症の疫学が初めて明らかとなり、診療・病態に関する多くの知見を得た。今回、学会主導でさらに大規模な重症敗血症に関する多施設共同前向き疫学調査研究を進める。本研究は重症敗血症の疫学、病態生理と臓器不全発症機序、診断・治療を詳細に検討し、日本の敗血症診療水準の再評価を目指す。
外傷
長く科学的根拠の乏しかった外傷診療にも、近年、いくつかのランダム化試験が報告されたが、短時間に決定的な診断治療の判断が迫られる外傷初期診療においてはランダム化試験を補完する観察研究の重要性はとりわけ高い。本研究では、病院前、ERから受傷後24時間に至るまでの初期診療情報と28日転帰を収集することで、外傷初期診療に寄与する科学的根拠の確立を目指す。
ARDS
急性肺損傷(ALI)および急性呼吸促迫症候群(ARDS)診断に米国欧州合意会議(AECC)の定義が用いられてきたが、2012年に新たなBerlin定義が公表された。欧米のメタ解析では死亡率が 44.3%との報告があるが、我が国の実態は不明である。本研究はAECC ALI、Berlin定義ARDSの疫学情報を収集することによりALI/ARDS診療の科学的根拠の確立を目指す。
市中劇症型感染症
標準的な治療では救命できない劇症型感染症の存在が明確化している。中でも肺炎球菌、レンサ球菌、黄色ブドウ球菌は市中劇症型感染症の原因菌として頻度が高いが、病態および劇症化の機序は解明されていない。本研究はこれら三菌の菌株収集と分子疫学解析を行うことで、対象感染症の劇症化と予後規定因子を解明して個別治療方法の確立を目指す。
熱傷
広範囲熱傷患者の初期診療には急速大量輸液が必要であり、米国熱傷学会ではバクスター公式の半分量から開始する新たな輸液法を近年推奨しているが、根拠となるエビデンスが明らかでない。従来のバクスター輸液法と米国熱傷学会提唱の輸液法のどちらが、広範囲熱傷患者における重篤な呼吸障害、急性腎不全、ACS等の有害事象発生が少ないのかを明らかにするために、多施設共同前向き無作為化比較対照試験を実施する。
2. 研究対象施設
日本救急医学会専門医指定施設(熱傷研究は日本熱傷学会熱傷専門医認定研修施設を含む)
3. 研究期間
委員会施設は2015年研究開始予定。
研究参加応募施設は2016年早々に研究開始予定。
研究期間
敗血症 1年
外傷 1年、予定症例数に満たない場合は1年延長
ARDS 1年
劇症型感染症 1年
熱傷 2年、予定症例数に満たない場合は1年延長
4. 研究結果の公表
日本救急医学会学会主導研究(JAAM FORECAST Group)として世界に公表する。同時に、日本救急医学会雑誌へ多施設共同研究特別委員会報告を公表する。